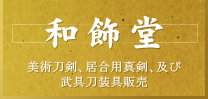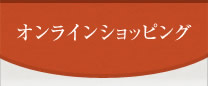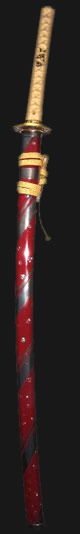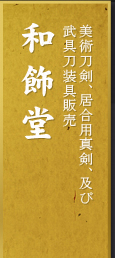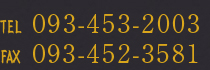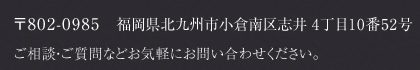「
日本刀の所持について」でも述べましたが、日本刀及び古式銃には必ず登録証が必要です。登録証のないこれらのものを所持したり、売買したりすると銃刀法違反となります。
しかしながら日本刀は皆様の想像以上に身近なものであり、屋根裏から先祖伝来の刀が出てきたという話や、父の遺品で登録証のない刀が出てきたという話は、世の中には少なくありません。この場合は、発見地を管轄する警察署の生活安全課に連絡し、「警察署に持ってきなさい」という指示のもとで、発見刀を発見地の警察署生活安全課に持参いたします。発見場所を警察が確認に行くこともありますが、ほとんどの場合はすぐに発見届けという書類を発行してもらえます。ほとんどの場合と申しましたが、もらえないケ−スもあります。
賢明な読者様はもうおわかりですね?そうです、発見した状況に嘘があると発見届け書類をもらうどころか、逆に大変なことになります。“大変なこと”の意味もわかりますね?とにかく発見したときの状況を、正直に話しさえすれば問題ありません。
さてこの発見届け書類をもらえたら、刀と共に都道府県が主催している刀剣等登録審査会に持って行くことになります。開催日は各県によって違いますが、概ね1ヶ月に1回行わ
れています。そこでその刀が真の日本刀であるかどうかが審査され、合格すると登録証がもらえます。不合格ですと警察署に提出しなければなりません。没収という流れになります。但し、その不合格刀に拵えが付いていれば、拵えまで没収されることはありません。
真の日本刀(合格の基準)とは、日本古来の鍛法により鍛えられたものであるか。刀の機能を失っていないか(刃がない、朽込みが激しく刀としての用をなさない)だけであり、これらを満たしていれば、登録証は発行してもらえます。例え再刃や偽名刀であっても登録証は発行され、偽名のままの銘を書いた登録証が発行されます。つまり登録証にある銘文というのは、単にそういう銘が切られているということに過ぎません。年期も同じです。ですからその刀の正真(銘通りの作者が製作したものか?)は、ご自身で研究するか、然るべき鑑定家、鑑定機関に見てもらうしかありません。
登録会場でよく問題となるのは、いわゆる軍刀です。太平洋戦争時代は、実際の武器としてのほか、指揮、戦意高揚、武人の誇りなどの意味で、夥しい数の日本刀が要求されましたが、戦場に持って行ける日本刀には、自ずと数に限りがあります。日本刀不足を解消するため、受命刀工制度などで日本刀生産に励んだのですが、刀工一人がトンテンカンと金槌を叩いて作れる日本刀の数は、たかが知れています。所詮は焼け石に水です。
そこで日本刀製作のノウハウがある、岐阜関あたりの伝統工芸が生きてきます。大きな工場で女工さんたちの手で、西洋鉄を材料にした単に日本刀の形に鉄をくり抜いたものを、油焼き入れして日本刀に似たものを生産しました。意味合いはナイフと同じですが、現在でも素人の方だと、日本刀との区別はつかないと思います。その他、満鉄刀(レ−ルなどを材料にした)、スプリング刀、興亜一心刀と色々ありますが、要は日本刀ではありません。逆に審査会とは、これらを合格させないためのものと言えます。ですから前述いたしました通り、これら以外だったらたいていのものは合格させるということです。
しかし、軍刀でも真の日本刀は存在しますので、話はややこしくなります。では審査員というのは、真の日本刀とこれら戦時中に製作された“日本刀もどき”との区別はつくのでしょうか?持ち込まれた審査物は個人の財産とはいえ、不合格となると国家権力に没収されるのですから任務は重大ですが、日本刀の経験が深い“具眼の審査員”なら簡単に判断できます。
まず“日本刀もどき”には鍛え肌がまったくありません。日本刀は和鉄を繰り返し、折りたたみ(折り返し)鍛錬をしますから、木の年輪のような鍛え肌が表れます。新々刀などは無地風のものもありますが、これとて立派に鍛えてありますので見えにくいといっても地肌はあります。あとは、茎に桜のマ−クの刻印があるとかで容易に判断できます。業者などが持ち込むものの中には、これらのマ−ク刻印を巧妙に消したものもありますが、無駄なことです。必ずと言っていいほど審査員は見抜きます。あとは参考程度ですが、軍刀拵えに装着されているケ−スが多いということもあります。審査員にとっては素延であることを見抜くのは容易ですが、これを申請者に納得させることの方が難しいようです。なにしろ相手は素人であり、持ち込まれたものはまったく日本刀と同じ形をしているのですから…。
しかし、これら日本刀でない軍刀に本物の登録証が発行されて流通しているケ−スはままあります。登録制度が始まったのは、昭和26年からですが、登録に関する法整備が未成熟の上、戦後間もなかったこともあり、戦地で生死をともにしたと申請者に言われたら、審査員も素延とわかっていても登録証を出すしかなかったでしょう。むしろ、登録制度が始まった大きな理由は、日本の文化遺産である日本刀を占領軍から守ろうとしたことにあります。現在はそういうこともなくなったので、純血種の日本刀のみを残すというスタンスに転換してきました。
登録会場にいくと、今でも軍刀の不合格の場面に出くわします。申請者は悪意のない素人ですので、審査員に向かって、「あんた、なにゆうてまんねん?これは、じいちゃんが満州で生死をともにした刀でっせ?これが日本刀でなくてなんだんねん?あんたにじいちゃんの苦労がわかりまんのか?裁判に訴えても、登録証はもらいまっせ…」と詰め寄る場面を目にすることも決して少なくありません。このときの登録会場は関西の某県でしたが、私の地元九州の方のためにこれを九州弁(博多弁)に翻訳いたしますと、「あんた、なんばゆうとっと?これはじっちゃんが満州で生死をともにした刀ばい。これが日本刀じゃなかけんゆうならなんちゅうと?きさんにじっちゃんの苦労がわかると?おいは裁判に訴えても登録証ばもらうけんね」となります。じっちゃんの苦労と登録証は何の関係もありません。また裁判に訴えても無駄なことです。審査員複数が日本刀でないと判断したら、日本国中のどこの裁判所にいっても通りません。もちろん訴えることは自由ですから、教育委員会は止めはしませんが…。
最後に一番大事なことですが、友人間で売買するときは、買う前に必ず登録証が本物かどうかを、各県教育委員会に確認してください。電話で登録番号や寸法銘文などを言うと、教育委員会の方が台帳と合致しているか教えてくれます。もう一つ大事なことは、登録証の内容と現物の寸法が合致しているかを自身で計って確認してください。偽物登録証は銘文が合っていても寸法が違うことが多いからです。なぜここまでしつこく言うかというと、それほど登録証の偽物も多いからです。刀剣店は登録証を確認していますので、刀剣店で買うのは登録証に関しては安心です(刀が正真かは別問題)。
登録証制度のことや内容を述べてまいりましたが、再発行などについては後日アップしてまいります。
登録のことでご質問がありましたらお気軽に当店にご質問ください。